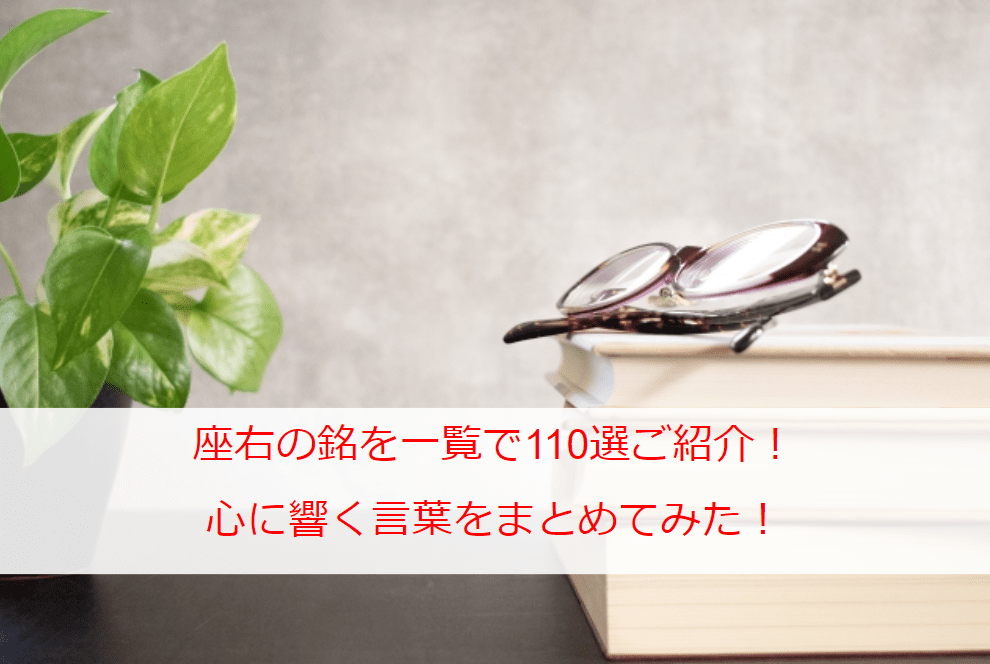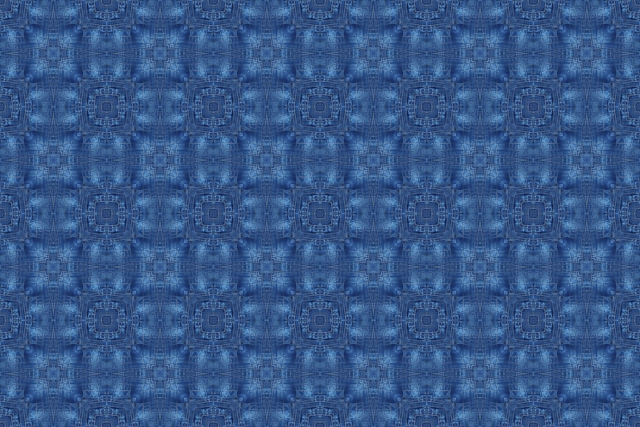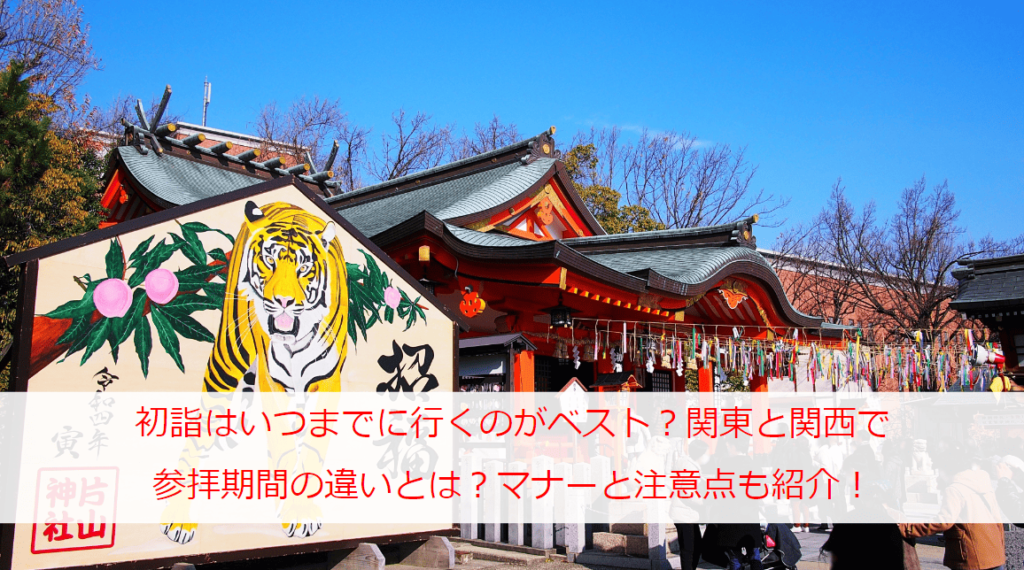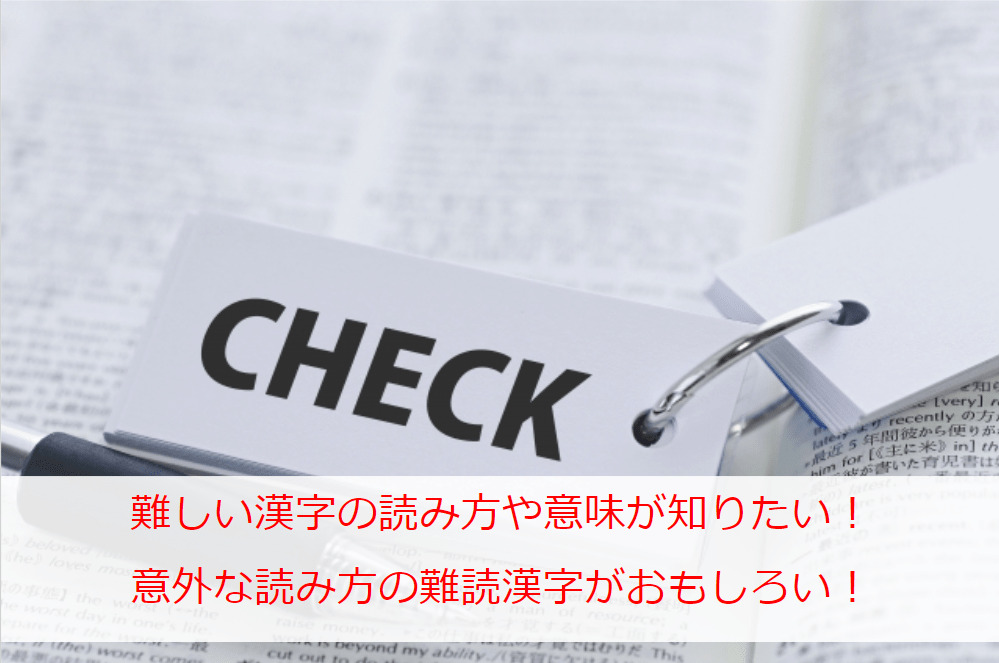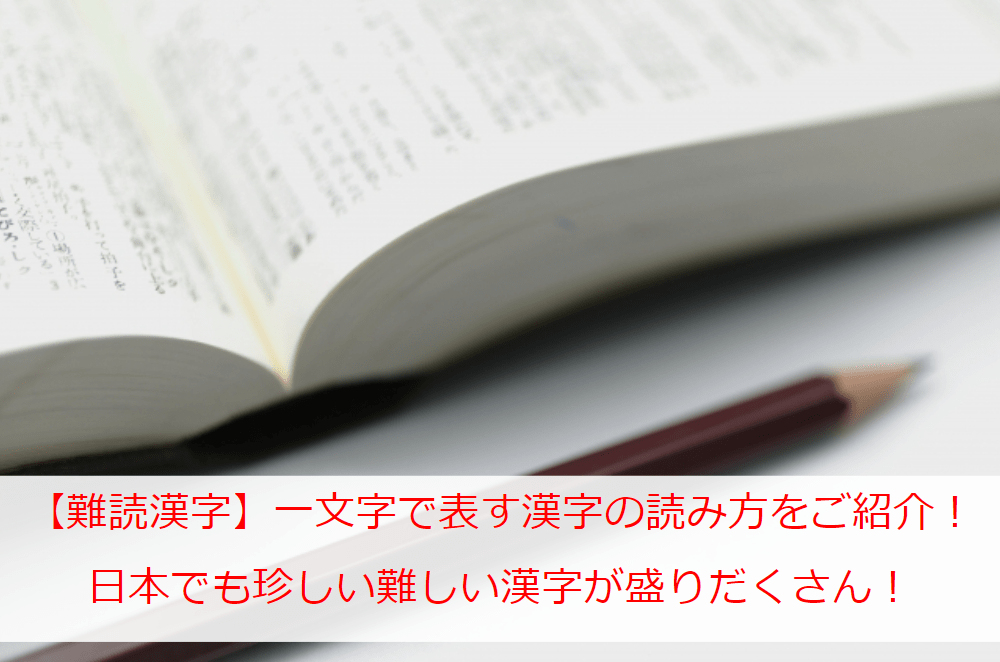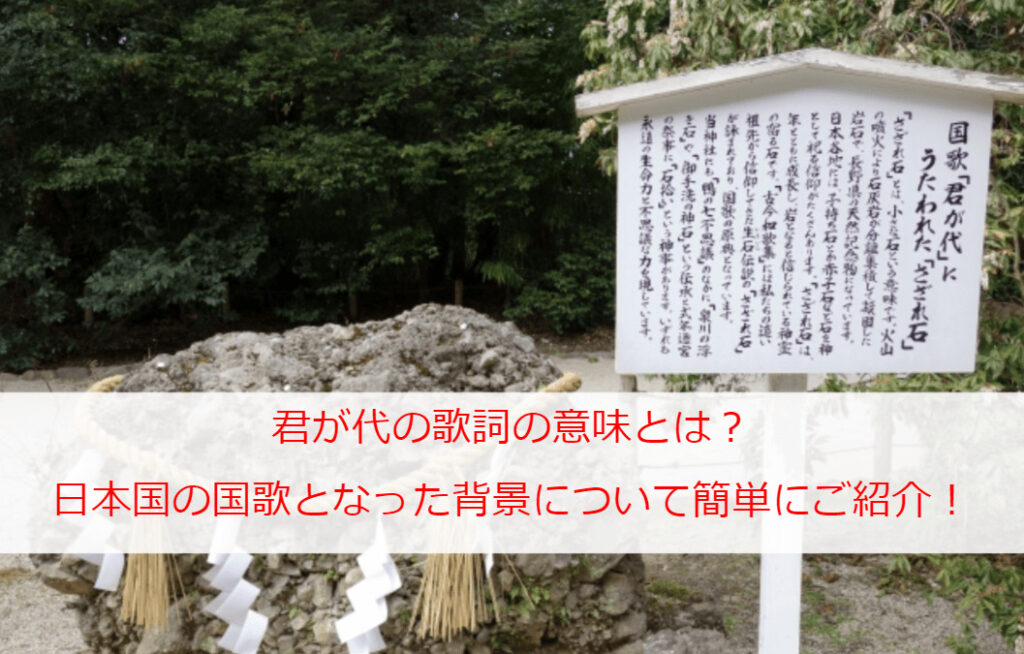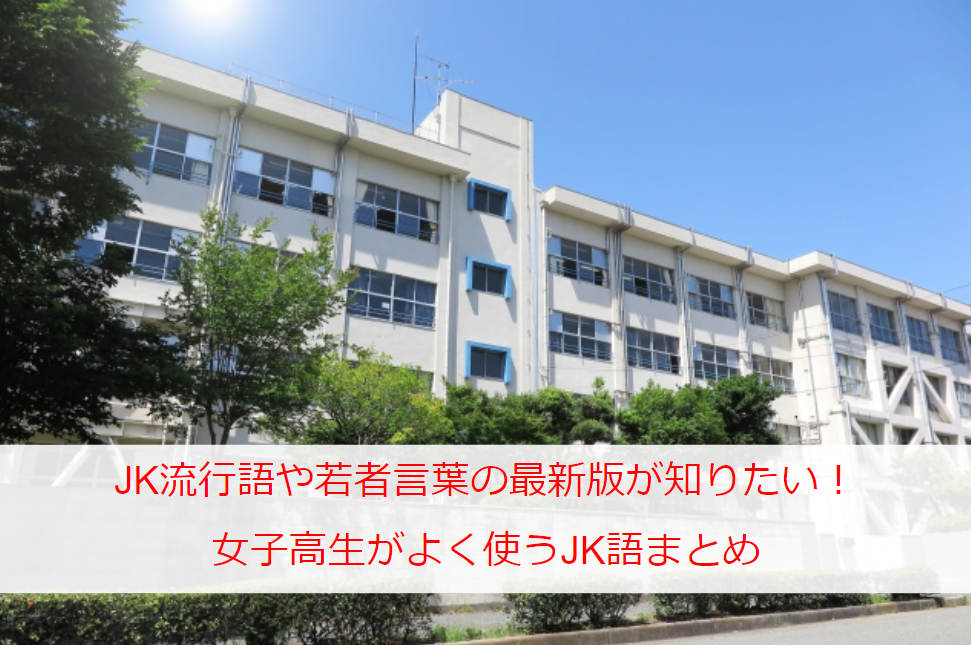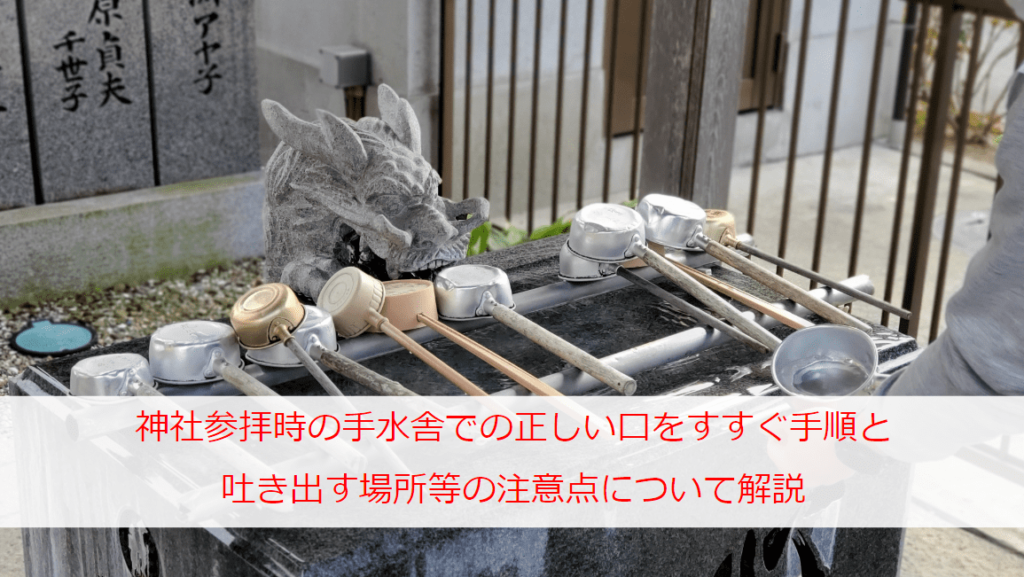【座右の銘にしたいおすすめ一覧110選】座右の銘とは?心に響く言葉シーン別人気6選や意味も簡潔にご紹介!
- 更新日:
- 公開日:
辛い時や頑張りたい時など、自分の支えとなってくれる「座右の銘」。敢えて自分の座右の銘がないという人も、これまでに勇気をもらった言葉などを思い浮かべてみましょう。昔から伝わることわざや古語などはもちろん、有名人や親しい人の発言なども良いですね。
今回は人気の高い座右の銘を110選ご紹介します。気分が沈んでいる時こそチェックしてほしい言葉が盛りだくさんですよ。
こちらの記事では、
- 座右の銘とは?
- 座右の銘にしたいおすすめ一覧110選!意味や読み方も簡潔にご紹介!
- 心に響く言葉シーン別人気6選も!
についてご紹介します。
座右の銘とは?
そもそも「座右の銘」とは、いったいどんな言葉を指すのでしょうか。
国語辞書を引くと、「いつも自分の座る場所のそばに書き記しておいて、戒めとする文句」と記載されています。人生において嬉しい時も辛い時も、この言葉を思い返して自分を律することができる……という言葉のことのようですね。
つまり座右の銘とは、自分の人生に大きな影響を与える言葉ということになります。たった1つの言葉を守り抜くも良し、いくつかの言葉を大切にするも良し、その時々で感銘を受けた言葉は覚えておくと良いですね。
▲ 目次に戻る
座右の銘にしたいおすすめ一覧110選!意味や読み方も簡潔にご紹介!

それではさっそく、座右の銘をご紹介していきましょう。古来から伝わる言葉をはじめ、誰もが知るあの人が発言した言葉も含まれています。
1. ア行
愛とは、育てなくてはならない花のようなもの(Love is like a flower – you’ve got to let it grow. John Lennon.)
読み方:あいとは、そだてなくてはならないはなのようなもの
「ジョン・レノン」の言葉。愛はただ投げかけるだけではしおれてしまうため、常に思いやりながら育んでいかなければならない。
愛は、敵を友人に変えられる唯一の力である(Love is the only force capable of transforming an enemy into a friend.)
読み方:あいは、てきをゆうじんにかえられるゆいいつのちからである
「キング牧師」の言葉。戦争の絶えない世界において、ただ一つ争いを止めることができるのが「愛」である。昨日まで敵だった相手も、愛さえあればすぐにわかり合うことができる。
青は藍より出でて藍より青し
▼藍色
読み方:あおはあいよりいでてあいよりあおし
優れた指導者に出会った弟子が、知識を習得し後に指導者よりも大成するという意味のことわざ。
▼藍の葉
浅い川も深く渡れ
読み方:あさいかわもふかくわたれ
浅い川に見えても、川の流れは複雑で流されてしまうこともある。常に深い川だと思い、慎重に渡れば安全に渡りきることができるという意味のことわざ。
明日は明日の風が吹く
読み方:あしたはあしたのかぜがふく
今日がいくらダメな日でも、明日は異なる一日になる。それならば今この瞬間だけを見つめ、大切にすることが望ましいということわざ。
明日の自分を信じる
読み方:あすのじぶんをしんじる
周りの誰も信じられなくても、自分のことは自分しか信じてあげられない。悩んだ末の決断を信じ、悩み過ぎないことも大切。
明日の百より今日の五十
読み方:あすのひゃくよりきょうのごじゅう
明日大きな利益を生むとしても、今日得られる少しの利益を確実に積み上げる方が安全だという考え。
雨垂れ石を穿つ(「水滴石を穿つ」、「点滴石を穿つ」と同義)
読み方:すいてきいしをうがつ(「すいてきいしをうがつ」、「てんてきいしをうがつ」)
あまだれでも、長年同じところに当たっていれば石に穴が空く。小さな努力でも長年続けることで大きな壁を突破できるということわざ。
雨降って地固まる
読み方:あめふってじかたまる
乾燥した地盤よりも、雨が降った後の水分を含んだ地盤は強固になることからきたことわざ。喧嘩やもめごとを繰り返した関係は、以前よりもずっと強いものになるという例え。
過ちて改めざる是を過ちと謂う
読み方:あやまちてあらためざるこれをあやまちという
失敗はそれそのものが悪いことなのではなく、失敗したことを改めようとせず諦めている姿勢こそが悪だという意味のことわざ。
言うは易く行うは難し
読み方:いうはやすくおこなうはかたし
口先だけで「やる」というのは簡単でも、実際に成し遂げるのは難しいという意味の言葉。やるやると口だけで並べ立てるのではなく、実際に成功してから自慢すべき。
怒りは無謀をもって始まり、後悔をもって終わる
読み方:いかりはむぼうをもってはじまり、こうかいをもっておわる
数学者「ピタゴラス」の言葉。怒りの感情は常に冷静ではなく「無謀」から始まっており、感情に身を任せた後には後悔することもしばしば。今一度深呼吸をして考え直し、行動を改めることが重要である。
生きてるだけで丸儲け
読み方:いきてるだけでまるもうけ
「明石家さんま」の言葉。この世界に生きているだけで、後はどんな不幸があろうとも乗り越えるチャンスが生まれるという意味。生きてさえいれば、人生はどんな方向にも転がっていくはずである。
意思あるところに道は開ける(Where there’s a will, there’s a way)
読み方:いしあるところにみちはひらける
アメリカ第16代大統領「リンカーン」の言葉。誰もが止めるような困難な夢も、活路を開くのは強い意思であると述べている。
石の上にも三年
読み方:いしのうえにもさんねん
いくら冷たい石であっても、三年座り続けていればあたたまる。同じように長年積み重ねた努力は必ず結果を生むということわざ。
「石の上にも三年」という。しかし三年を一年で修得する努力を怠ってはならない
読み方:いしのうえにもさんねんという。しかしさんねんをいちねんでしゅうとくするどりょくをおこたってはならない
Panasonic創業者「松下幸之助」の言葉。長い間努力を積み重ねていればいつか叶うが、その期間を短縮するために工夫を凝らすことこそが「努力」であると述べている。
石橋を叩いて渡る
読み方: いしばしをたたいてわたる
強固なはずの石でできた橋も、万が一落ちても良いように叩いて渡るほど慎重に過ごすという意味。何を行うにも用心するに越したことはなく、常にリスクを考えながら行うことが大切。
急がば回れ
読み方:いそがばまわれ
遠回りをせずリスクを冒して近道を選ぶと、結果トラブルが起こり事態が長引くことも多い。急いでいる時だからこそ、確実にリスクの少ない道を選ぶべきである。
一期一会
読み方:いちごいちえ
「千利休」の考えからきている言葉。今目の前にいる人は、人生でたった一度しか会わないかもしれない人であるため、その分大切にしたいという考え。
一念、天に通ず
読み方:いちねん、てんにつうず
たった一つの強い願いを繰り返していると、天に通じて願いが叶うという意味の言葉。何をするにも重要なのは、「成し遂げたい」という強い気持ちに他ならない。
一陽来復
読み方:いちようらいふく
「陽」はまた昇る、すなわち悪い出来事が続いてもいつかはいい出来事が巡ってくるという意味の四字熟語。
一所懸命
読み方:いっしょけんめい
短文でありながら直球な言葉。この瞬間を命がけでやり遂げるという強い意思が込められている。
一寸の光陰軽んずべからず
読み方:いっすんのこういんかろんずべからず
たった一瞬の間に起こった出来事でも、その積み重なりで人生ができている。自分を形成している全ての事柄を軽んじてはならないという意味のことわざ。
いつも柳の下に泥鰌はおらぬ
読み方:いつもやなぎのしたにどじょうはおらぬ
一度美味しい思いをしたとしても、また同じことがあるとは限らない。方法を変えるなどの工夫をしなければ成功し続けることはできないのである。
井の中の蛙大海を知らず
読み方:いのなかのかわずたいかいをしらず
小さな井戸の中の蛙は、広い海の存在すらも知らない。転じて、狭い世界の中で生きているだけでは、周りで何が起こっているのかわからずに損をするという意味のことわざ。
魚心あれば水心
読み方:うおごころあればみずごころ
相手の気持ち次第で自分の気持ちも変わるという意味の言葉。転じて、相手がやりたいと思うのなら自分もついていく、また相手が自分を信頼してくれるのならば自分も信じる、という意味で使われる。
雲外蒼天(「雲外に蒼天あり」ともいう)
読み方:うんがいそうてん
雲が立ち込めるようなトラブル続きの日々でも、それを乗り越えれば青空のように晴れ渡る日々が広がっているという意味のことわざ。辛いことはいつまでも続かず、いつか終わる日が来るはず。
縁の下の力持ち
読み方:えんのしたのちからもち
一見目につかないようなところで頑張っている人のたとえ。普段目立たない人が、実際は重要な基盤を担っていたということもよくあるもの。トップに立つ人だけが頑張っているわけではないと知ることが大切である。
起きて半畳寝て一畳
読み方:おきてはんじょうねていちじょう
起きている時は半畳ほど、寝る時は一畳のスペースがあれば十分である。転じて、生活に必要なもの以外は高望みしすぎることなく、質素な生活こそが重要だという考え。
思い立ったが吉日
読み方:おもいたったがきちじつ
せっかく思いついたアイディアも、数日経った後では霞んで見えるもの。何かをやろうと思ったらすぐに始めるのが良いという例え。
終わり良ければすべてよし(All’s well that ends well!)
劇作家「シェークスピア」の作品に由来する言葉。どれだけ手を加えた作品も、終わり方が悪ければすべてが台無しになってしまうため、最後まで気を抜かずやり抜く必要がある。
温故知新
読み方:おんこちしん
古いと思われている知識の中から、新たな発見があるという意味の四字熟語。先人の教えは軽んじて良いものではなく、また古い知識ばかりを頼り切っていても良くない。
2. カ行
変えるにはリスクが伴う。変えなければもっと大きなリスクが伴う(Risky to change. Riskier not to change.)
宇宙飛行士「ジョン・ヤング」の残した言葉。何も変えずにいるのは安泰なように見えて、いずれ後悔してもしきれないほどの大事に発展してしまうという意味がある。
臥薪嘗胆
読み方:がしんしょうたん
硬い薪の上で寝たり、苦い胆をなめたりといった苦行を成し遂げながら、いつか来たる成功の日を待ちわびることのたとえ。成功の為ならどんな苦しみも耐える、という意味にもとれる。
鴨の水掻き
読み方:かものみずかき
水面にただ浮かんでいるように見える鴨も、実は絶えず水をかきながら浮かんでいる。すました顔で仕事をこなしているように見える人も、影ながら努力しているという意味のことわざ。
艱難汝を玉にす
読み方:かんなんなんじをたまにす
困難な道を選んでこそ、人間として魅力的に成長できるということわざ。楽な道ばかりを選んでいては、ここぞという時に使えない人間となってしまう。
「艱難(かんなん)」とは、困難に出会って苦しみ悩むことです。
聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥
読み方:きくはいっときのはじ、きかぬはいっしょうのはじ
分からない点を聞くのは時に恥ずかしいことだが、後々聞かずにいたことで失敗をすればより一層辱めを受けることとなるという意味のことわざ。
昨日から学び、今日を生き、明日へ期待しよう(Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow.)
物理学者「アインシュタイン」の言葉。昨日過ごした一日を無駄にせず、経験から学んで今日へ活かすこと。そしてまだ見ぬ明日を思って不安を抱えるのではなく、希望を胸に明日を迎えたいという意味を持つ。
窮すれば通ず
読み方:きゅうすればつうず
どうしようもなくなった時こそ、自然と道は開けるものである。最後まであきらめることなく解決方法を探すことが重要。
恐怖は常に無知から生じる(Fear always springs from ignorance.)
思想家「エマーソン」の言葉。何かを怖いと思うのは、それについてよく知らないからであるという意味を持つ。恐れずに踏み出してみると、案外怖いものではない場合も多々あるのだ。
鶏口となるも牛後となるなかれ
読み方:けいこうとなるもぎゅうごとなるなかれ
小さな集まりの中で集団を率いることは、大きな集まりの中で有象無象となるよりも経験を育むことができるという意味のことわざ。
結果の平等はともかく、機会というものは誰にでも平等であると固く信じている(I’m a very big believer in equal opportunity as opposed to equal outcome.)
Apple社を設立した「スティーブ・ジョブズ」の言葉。彼は決して特別恵まれた人間だったわけではなく、誰しもが平等に与えられたチャンスを使ってのし上がったに過ぎない。
限界なんてない
読み方:げんかいなんてない
限界という言葉はただの飾りで、自分が勝手に決めたラインである。実はその先にも道が広がっているのに、限界だからと諦めてしまってはもったいない。
捲土重来
読み方:けんどちょうらい
一度戦いに敗れた者ほど、恐ろしい勢いで巻き返しやがて勝者となるという四字熟語。悔しい思いを経験した人の方が粘り強く、最終的に成功を収めるのである。
行動しなければ始まらない
読み方:こうどうしなければはじまらない
失敗を恐れるあまりに悩み過ぎて結果行動できずにいると、それは何もしなかったのと同じことである。まずは何事もチャレンジし、経験を積むことが大切である。
弘法筆を選ばず
読み方:こうぼうふでをえらばず
真言宗の祖「弘法大師」の生き様からきた言葉。どんなに粗悪な筆でも美しい文字を書いた弘法大師を見て、その道のプロはやり方や道具に関わらず素晴らしいものを生み出すという意味の言葉が生まれた。
心安きは不和の基
読み方:こころやすきはふわのもと
いくら親しいからといって、相手のことを考えずに無遠慮なふるまいばかりをしていると関係が崩れてしまう。親しいからこそ気遣いの心をなくしてはならない。
転ばぬ先の杖
読み方:ころばぬさきのつえ
転んでから初めて杖を準備していたのでは遅すぎるため、いつ転んでもいいように杖を持っておくということわざ。つまり、いつ何があっても良いように常より準備を怠らないことのたとえ。
困難に直面したのなら、溺れるか、泳ぐかのどちらかしかないんだ(When you have to cope with a lot of problems, you’re either going to sink or you’re going to swim.)
俳優「トム・クルーズ」の言葉。困難に直面した人ができるのは、「立ち向かう」か「諦める」かの2択である。それ以外に道はないのだから、受け入れて立ち向かうのがもっとも有効な手段である。
3. サ行
酒と朝寝は貧乏の近道
読み方:さけとあさねはびんぼうのちかみち
酒を飲み漁り朝になってようやく寝るような生活は、だらしないだけでなく貧乏に繋がるということわざ。朝までダラダラと飲み続け酒代がかかるだけでなく、仕事も思うようにならず生産性も下がるという意味。
下を向いていたら、虹を見つけることは出来ないよ(You’ll never find a rainbow if you’re looking down.)
「チャップリン」の言葉。悲しいことがあったからといって下ばかり向いていたら、起きていたはずの幸福にも気がつくことはできない。悲しい時こそ顔を上げ、前を見据えて生きるべきである。
七転八起
読み方:しちてんはっき
何回トラブルに遭って転んでも、再び立ち上がりチャレンジするという意味の言葉。くじけずに何度も立ち向かう姿勢こそ、物事をやり遂げるのに必要なことである。
質実剛健(「剛健質実」ともいう)
読み方:しつじつごうけん(ごうけんしつじつ)
質素かつ堅実であり、強さやたくましさを兼ね備えている様子を表す言葉。スポーツマンなどを褒める際にも使われる。
失敗と書いて、成長と読む
読み方:しっぱいとかいて、せいちょうとよむ
選手であり監督であった「野村克也」の言葉。失敗を経て大きくなっていくのは子どもも大人も同じで、指導者に必要なのは失敗をどう生かすかといったことだ、という意味を持つ。
失敗は成功のもと
読み方:しっぱいはせいこうのもと
なぜ失敗したのか、どうしたら失敗しないのかを考えることで初めて成功が生まれる。成功することばかりを考え失敗を恐れていては成功できないということわざ。
死ぬこと以外かすり傷
読み方:しぬこといがいかすりきず
取り返しのつかないミスをして落ち込んだとしても、それが生命を脅かす可能性は低いもの。命さえあれば何度でもやり直しができるため、前を向かなくてはならないという意味の言葉。
自慢高慢馬鹿の内
読み方:じまんこうまんばかのうち
自分の才能や経験をひけらかしたり、周りの者を下に見たりする行為は馬鹿のすることである。つつましく生きてこそ周りの魅力に気がつけるといった意味のことわざ。
習慣は第二の天性なり
読み方:しゅうかんはだいにのてんせいなり
持って生まれた特性はもちろん、普段の習慣も人を成長させるポイントの一つ。才能の有無だけに固執せず、日々清く正しく生きることが大切。
小事に拘わりて大事を忘るな
読み方:しょうじにかかわりてだいじをわするな
仕事や勉強をしていると、次々に降りかかる小さなトラブルに目が行きがち。しかし物事の本質を見抜き、もっとも重要なことを忘れてはならない。
少年老い易く学成り難し
読み方:しょうねんおいやすくがくなりがたし
何か物事を学ぶのには、若いうちこそがふさわしい。年を取ってから何かを学ぼうと思っても、若い頃とは比べ物にならないほど処理能力が落ちている。つまり、時間の限られている若いうちこそ何事にも挑戦すべきという意味。
初志貫徹
読み方:しょしかんてつ
何かを始める際に決めたことは、変更せず最後までやり遂げるという意味の四字熟語。たとえ難しい内容でも、簡単に諦めることなく最後までやり抜こうという精神が重要。
初心忘るべからず
読み方:しょしんわするべからず
何かを始める時はまっすぐな気持ちを持っていても、慣れてくれば傲慢になってしまうもの。常に始まりの頃の自分を忘れず、背筋を伸ばして物事に取り組むことが大切である。
神色自若
読み方:しんしょくじじゃく
どんなに大事であっても冷静さを失わず、自分を見失うことがないという意味の四字熟語。大変なときこそ慌てずに、落ち着いた判断をすることが重要。
人事を尽くして天命を待つ
読み方:じんじをつくしててんめいをまつ
できることは全て行った後は、神による采配を待つのみであるという意味。後は祈るのみ、というところまでやりきることの大切さを説いたことわざ。
迅速果断
読み方:じんそくかだん
あれこれ迷わず、決めるべきときはすぐに決断できるという意味の四字熟語。運やタイミングを逃さないよう、普段から早めの決断を心掛けることが大切である。
真の男は誰に対しても憎しみをもたない
読み方:しんのおとこはだれにたいしてもにくしみをもたない
「ナポレオン」の言葉。本当に男らしいということは、誰と比べることもなく、全ての個性を受け入れ尊重するということである。
好きこそ物の上手なれ
読み方:すきこそもののじょうずなれ
何をするにも、その道が好きでやっている人には敵わないということわざ。好きな道を仕事にしたい場合などにも用いられる。
成功するためには、これがいつも最後だと思ってトライすることだ
Nikeの創業者「フィル・ナイト」の言葉。今日が人生最後の一日だと考えれば、行うこと全て全力でできるはずである。そのくらい気持ちを向けなければ、大きな成功などあり得ないという意味が込められている。
青年は老人を阿呆だと思うが、老人も青年を阿呆だと思う
詩人「チャップマン」の言葉。お互いが阿呆だと思い合っている若者と老人だが、実はお互いに敬い合うことができる存在でもある。しかしそれがうまくいかないのは、いつの時代も同じことのよう。
千里の道も一歩から
読み方:せんりのみちもいっぽから
千里という途方もない距離を歩き始める時も、最も重要なのは一歩を積み重ねることであるということわざ。
損して得取れ
読み方:そんしてとくとれ
小さな損を積み重ねてでも、いずれやってくる大きな得を得た方が利益が大きいという意味のことわざ。リスクを避けながらでは、大きな運にも巡り会えないままである。
4. タ行
高く登ろうと思うなら、自分の脚を使うことだ!
哲学者「ニーチェ」の言葉。現在よりもステップアップするためには、他人を当てにしていてはいつまでも叶わないもの。自分の足で行動してこそ未来を掴み取ることができる。
鷹は飢えても穂を摘まず
読み方:たかはうえてもほをつまず
鷹のように節度を持って過ごしている人は、たとえどんなに苦しくても他人の持ち物を奪わないという意味。人を苦しめてまで自分が助かろうとするのは、傲慢な人間のすることである。
立つ鳥跡を濁さず
読み方:立つ鳥跡を濁さず
その場から立ち去る者は、まるで何もなかったかのように颯爽と去っていくべきであるということわざ。未練を残すのはもちろん、トラブルを残してその場を去るのは言語道断である。
楽しまずして何の人生ぞや
作家「吉川英治」の言葉。自分が自分として生きる人生はたった一度きりにもかかわらず、人は辛く苦しい道を選ぶことが多いもの。楽しんでこそ有意義な人生を送ることができるのである。
旅は道連れ世は情け
読み方:たびはみちづれよはなさけ
人生はたった一人で生きていくことはできないため、情けをかけあって人との関わりを大切にしなければならないという意味のことわざ。
塵も積もれば山となる
読み方:ちりもつもればやまとなる
例え小さな努力であっても、積み重ねていくうちに他者をも凌駕する大きな結果を生むということわざ。逆に、小さなミスだと思って見逃しているうちに大事になってしまう……という意味にもとれる。
敵は己の中にあり
読み方:てきはおのれのなかにあり
失敗ばかりでつい他人を責めたくなってしまうときは誰にでもあるもの。しかし失敗の原因は自分にあるなど、まずは自分の行動を振り返るのが大切。
鉄は熱いうちに打て
読み方:てつはあついうちにうて
考えがこり固まった人よりも、始めたばかりの柔軟なころの方が改めやすいという意味。物事を始めるのはもっともやる気のある最初がふさわしく、タイミングを間違えれば成功できないこともある。
時は金なり
読み方:ときはかねなり
同じ時を過ごす場合でも、有意義に過ごすか怠惰に過ごすかでは大きく結果が異なる。金を生むのも、結局は「有意義な時間」なのである。
独立独歩
読み方:どくりつどっぽ
誰からの助けも必要とせず、自分の力だけで生きていることのたとえ。誰かを当てにするのではなく、できる限りは自分でやるという強い信念を感じさせる言葉でもある。
努力する人は希望を語り、怠ける人は不満を語る
作家「井上靖」が残した言葉。口から発する言葉はやがて言霊となり、その人となりを表す言葉へと変わっていく。
努力は人を裏切らない
読み方:どりょくはひとをうらぎらない
たとえ努力の末に成功できなくても、努力した経験が無駄になることはない。人間として成長できるのは努力した人間だけだということわざ。
5. ナ行
為せば成る、為さねば成らぬ何事も
読み方:なせばなる、なさねばならぬなにごとも
できないと思っていてはいつまでたってもできないままだが、いざ「できる」と思ってやれば案外できてしまうものだという意味。不安ばかり気にせず、まずはチャレンジしてみることが大切である。
習うより慣れろ
読み方:ならうよりなれろ
いくら勉強をして知識を得ても、実際に体を動かして染みついた習慣には敵わないという意味のことわざ。
人間万事塞翁が馬
読み方:にんげんばんじさいおうがうま
これから何が起こるかは誰にもわからず、それが良いことなのか悪いことなのかすらも誰にも予言できないという意味。
能ある鷹は爪を隠す
読み方:のうあるたかはつめをかくす
才能を持っている人ほど、それをひけらかすことなく重要な場面でのみ力を発揮する。常より自分の能力を過信して自慢することのないように心がけたい。
6. ハ行
背水の陣
読み方:はいすいのじん
もう逃げられないほどに追い詰められた時こそ、全力で立ち向かうことができるという意味の言葉。
早起きは三文の徳
読み方:はやおきはさんもんのとく
早起き、つまりは健康的な生活をすることは、思っているよりも良いことがたくさんあるという意味のことわざ。
人には添うてみよ馬には乗ってみよ
読み方:ひとにはそうてみようまにはのってみよ
人柄の良し悪しは付き合ってみなければ分からないし、馬には実際に乗って乗り心地を試してみなければ良い馬かどうかすらわからない。実際に確認してみなければ、何事も真髄を知ることはできないということわざ。
人の振り見て我が振り直せ
読み方:ひとのふりみてわがふりなおせ
誰かから言われるまで何もせずにいるより、周りの人間が指摘されたことを自分に当てはめて直すことも大切であるという意味のことわざ。
人は考える葦である
読み方:ひとはかんがえるあしである
フランスの自然哲学者「パスカル」による言葉。葦という植物は1本1本は弱くても水辺でたくましく生きる植物でもある。そんな強さともろさ、そして考える大切さを人間は兼ね備えているという意味の言葉。
人を批評していると、人を愛する時間がなくなります
「マザー・テレサ」の言葉。人間に与えられた時間は有限であり、その中で人の粗探しばかりしていると貴重な時間を無駄にすることになる。せっかく同じ時間を過ごすのならば、人を愛するために使うべきである。
百聞は一見に如かず
読み方:ひゃくぶんはいっけんにしかず
繰り返し学び聞いたことよりも、一度目で見たことの方が頭に入りやすいという意味のことわざ。机に向かっている時間を少し割いて実習に当てると、より効率的な勉学が可能となる。
百里を行く者は九十里を半ばとす
読み方:ひゃくりをゆくものはくじゅうをなかばとす
何かを成し遂げようとするとき、半分過ぎたところで気を抜くのではなく、9割方終わるまで集中しなければならないということわざ。途中で慢心していては、百里の道を達成することはできない。
不撓不屈
読み方:ふとうふくつ
たとえどんなに高い壁であろうとも、超えていける強い精神力を持っていることのたとえ。
不言実行
読み方:ふげんじっこう
「あれもやりたい」「これもやりたい」と目標ばかりを口にしているよりも、黙って黙々とこなす人の方が重宝されるという意味の四字熟語。
僕が目指すのは自分
フィギュアスケート選手「羽生結弦」の言葉。類まれなる記録を打ち立ててきた彼だからこそ、ライバルではなく常に自分自身を超えるよう自らに言い聞かせてきた言葉でもある。
7. マ行
蒔かぬ種は生えぬ
読み方:まかぬたねははえぬ
種をまかなければ何も生えないのは当たり前。何もせず待っていても成功はなく、行動を起こすことが重要という意味のことわざ。
難しいのは愛する技術ではなく、愛される技術である
フランス人作家「ドーデ」が残した言葉で、人を好きになるよりも好かれることの方がはるかに難しいという意味を持つ。信頼関係も同じことで、いくら相手のことを信頼していても、相手から信頼されなければ友情を築くことはできない。
無欲は怠惰の基である
読み方:むよくはたいだのもとである
経済の父「渋沢栄一」がモットーとしていた言葉で、何も望まずにいれば次第と前を向く力すらなくなってしまうと述べたもの。欲があるからこそ、人間はさらに成長することができるのである。
求めよさらば与えられん
読み方:もとめよさらばあたえられん
新約聖書の言葉。強く願い欲する者こそが、本当に願うものを与えられるという意味。
物言えば唇寒し秋の風
読み方:ものいえばくちびるさむしあきのかぜ
人の噂には悪い内容のものが多く、いい結果を生まないため辞めるべきだという意味の俳句。悪口を言った相手だけでなく、自分までもが汚名を着せられることになりかねない。
8. ヤ行
有言実行
読み方:ゆうげんじっこう
口に出したことは必ず最後までやり遂げるという強い意思が大切、という意味の四字熟語。「やる」といってやらないのは、初めから何も決意していないのと同じことである。
雄弁は銀 沈黙は金(Speech is silver, silence is golden.)
読み方:ゆうべんはぎん、ちんもくはきん
英国の思想家トーマス・カーライルが広めた英語の諺である。誰しもが頷くような話ができるのは能力の一種であるが、それ以上に「黙っていることができる」のは難しく価値のあることであるという意味。
夢見ることができれば、それは実現できる(If you can dream it, you can do it!!)
ディズニー創業者「ウォルト・ディズニー」の言葉。彼の頭の中で思い描いていたファンタジーの世界は、今や数々の作品やディズニーリゾートとなって世界中で花開いている。
9. ラ行
リスクのない人生なんて、逆にリスクだ
サッカー選手「本田圭佑」の言葉。さまざまな分野にチャレンジした彼だからこそ言える一言で、チャレンジするリスクのない人生など面白味もなく、有意義に過ごせないという「リスク」を背負っているのと同じだという意味。
10. ワ行
私は決して負けない。勝つか、学ぶかだ(I never lose. Either I win or learn.)
ノーベル賞受賞者「ネルソン・マンデラ」の言葉。人種差別に立ち向かったことでも知られる彼が、常に自分を奮い立たせられるよう胸に刻んでいた言葉でもある。
笑う門には福来る
読み方:わらうかどにはふくきたる
普段から笑顔の絶えない場所には、自然と幸福が集まってくるということわざ。よく笑う人は周りを笑顔にできる人であり、トラブルしらずであることも多い。
笑われて、笑われて、強くなる
作家「太宰治」の言葉。誰に何といわれようとも、自らの意思を貫いた人こそが真の強さを得る。反対に人を簡単に笑うような人は、いつになっても強くなることはできない。
▲ 目次に戻る
心に響く言葉シーン別人気6選も!

それぞれの座右の銘は、意味によってどんな時に力になってくれるかが変わります。ここでは心に響くシチュエーション別に座右の銘をカテゴライズしてみますね。
自分を変えたいあなたにおすすめの座右の銘
- 明日の自分を信じる
- 思い立ったが吉日
- 昨日から学び、今日を生き、明日へ期待しよう。
- 習慣は第二の天性なり
- 初心忘るべからず
- 挑戦する機会というものは誰にでも平等である。
人生の岐路に立つなど重大な選択を迫られているあなたにおすすめの座右の銘
- 一寸の光陰軽んずべからず
- 変えるにはリスクが伴う。変えなければもっと大きなリスクが伴う。
- 艱難汝を玉にす
- 聞くは一時の恥聞かぬは一生の恥
- 失敗は成功のもと
- 損して得取れ
いつも明るくいたいあなたにおすすめの座右の銘
- 明日は明日の風が吹く
- 生きてるだけで丸儲け
- 窮すれば通ず
- 下を向いていたら、虹を見つけることは絶対に出来ないよ。
- 楽しまずして何の人生ぞや。
- 求めよ、さらば与えられん
頑張る力がほしいあなたにおすすめの座右の銘
- 雨降って地固まる
- 石の上にも三年
- 雲外に蒼天あり
- 限界なんてない
- 七転八起
- 成功するためには、これがいつも最後だと思ってトライすることだ。
人とのかかわりがほしいあなたにおすすめの座右の銘
- 愛とは、育てなくてはならない花のようなもの。
- 愛は、敵を友人に変えられる唯一の力である。
- 一期一会
- 心安きは不和の基
- 人を批判していると、人を愛する時間がなくなります。
- 笑う門には福来る
▲ 目次に戻る
まとめ

今回はさまざまな種類の座右の銘についてご紹介しました。ふと思い出すだけで、自分を取り戻せるような気持ちになる座右の銘。常に頭の隅に置いておき、日々生きる中で大切にしていきたいですね。